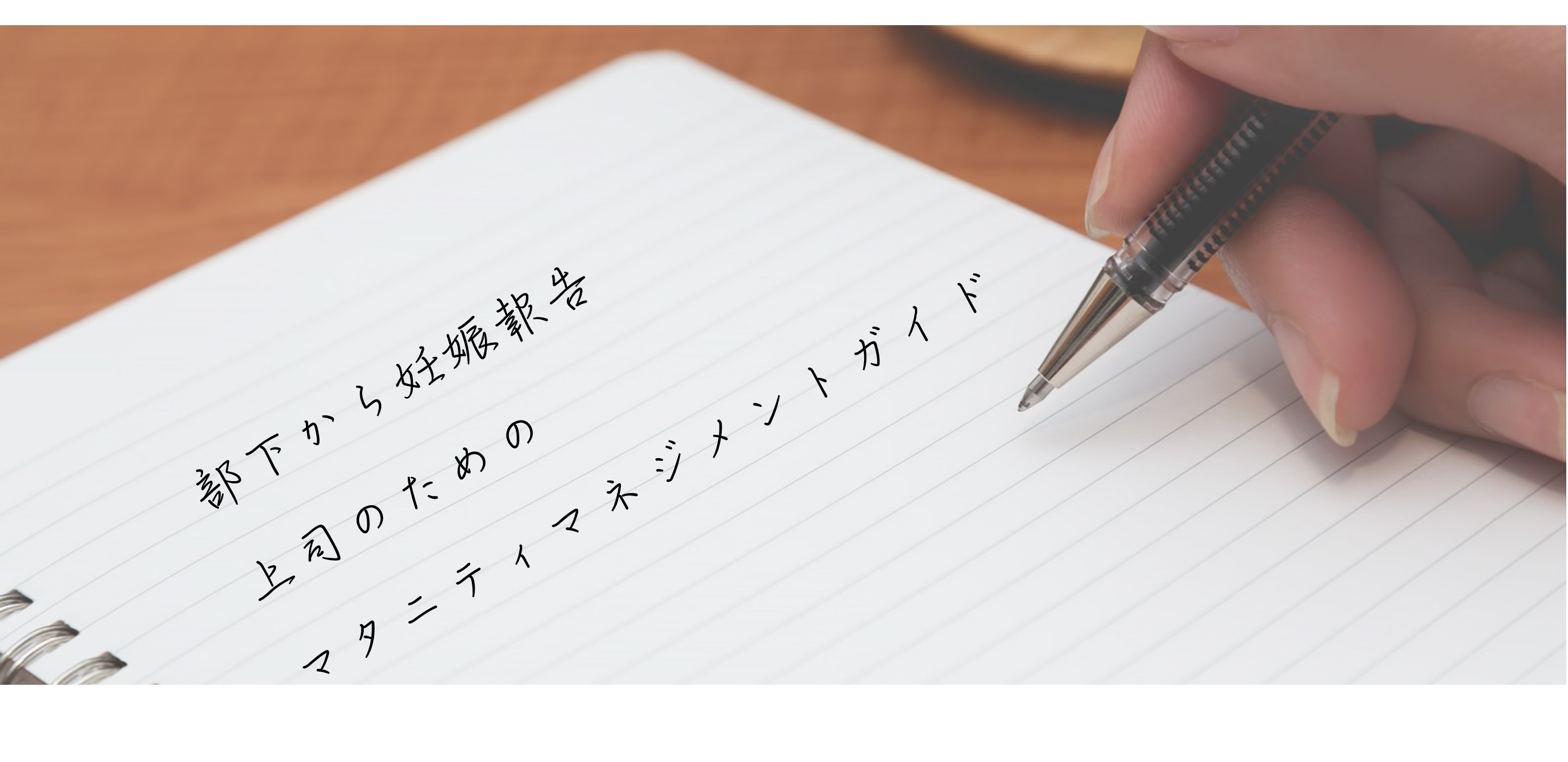社員が妊娠すると産前産後休業を取得したり、育児休業を取得することになります。業務の引継ぎが必要になり、さらに体調に配慮し現在進行中の業務について他の社員に分担させなければならない必要も出てくるでしょう。そのため引継ぎや分担について少しずつ準備をする必要があります。
スポンサーリンク
出産後も働き続ける意思があるかどうか
多くの社員が働き続けることを選択すると思われます。ただ社員の体調や考え方によっては退職を視野に入れている場合もあります。社員によってはすぐに決められないこともあるでしょう。

引継ぎや分担、さらには人員の補充についても検討しなければなりません。焦らず慎重に今後の意思について確認したいものです。
休暇を取得する期間について
下記サイトにて出産予定日を入力すると産休・育休期間について表示されます。
出産予定日と産休の予定
まず出産予定日を確認しましょう。予定日に基づき、産前産後休業について計算します。産前休業は出産予定日を含めて6週間、産後休業は出産日の翌日から8週間です。
育休を取得するのであればその期間
育児休業の取得は必須ではありませんが、取得を希望する社員が大多数となるでしょう。育児休業は子が1歳になる誕生日の前日まで取得可能です。保育園に入れない等やむを得ない事情があれば最長で2歳の誕生日の前日まで取得できます。
妊娠中、業務を変更する必要の有無
妊婦が請求した場合、他の軽易な業務に転換しなければなりません。妊婦が仕事内容が事務等のデスクワークであれば体への負担は少ないので配置転換の必要はほとんどないでしょう。力仕事や立ち仕事、営業での外回り、病院等で感染症の恐れがある場合などは、業務の軽減を図る必要があり、場合によっては別部署への配置転換も必要になってきます。労働基準法の『危険有害業務の就業制限』と『軽易業務転換』によって定められています。